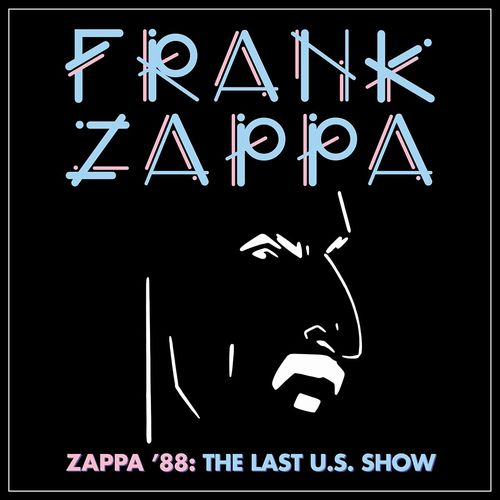今年、ついにフランク・ザッパ1988年のコンサートの一つが、まるまる一本、公式音源としてリリースされました。1988年と言えば、「Broadway The Hard Way」、「The Best Band You Never Heard In Your Life」、「Make A Jazz Noise Here」と3タイトル、CD5枚分の音源がリリースされており、その他「You Can’t Do That On Stage Anymore」などに分散して収録されていましたが、いずれも生前にザッパの手によってリリースされている分、一つのコンサートを初めから終わりまでノーカットで納めたようなものはなく、何らかのコンセプトに基づいて編集されたものばかりでした。どの作品も名盤と言って差し支えないクオリティとは言え、この1988年ツアーの全容を知れば知るほど、この程度の内容では到底満足できるものではありません。希望としては、1988年ツアーのコンプリート・ボックスを出してもらいたかったですが、それでも一つのコンサート、一部別のコンサートの音源に差し替えているとは言え、ほぼ追体験できるソフトとしてリリースされたことは、大変喜ばしいことです。
1988年のツアーの背景
1988年のザッパのツアーは、ファンにとってあらゆる意味で重要です。まず、彼にとっての最後のツアーとなったことが挙げられます。6月9日のイタリアでの公演を最後にバンド内のいざこざで終止符が打たれたこのツアー以降、彼はシンクラヴィアでの作曲、過去音源の編纂、そして癌の闘病に終始することになります。アンサンブル・モデルンとの1992年のツアーで何度か指揮台に立ちはしましたが、彼がバンドをAKAIサンプラーの如く自在に操り、自由奔放にギターソロを披露したのは、このツアーが最後でした。
ザッパ自身、その前の1984年のツアーで、ロックバンドでのツアーはもう区切りをつけるつもりだったようですが、1988年の大統領選に向けて、「途中休憩の間に観衆に選挙人登録をさせる」という政治的コンセプトを伴った最後のツアーバンドを結成することになりました。
トランペット(ウォルト・ファウラー)、トロンボーン(ブルース・ファウラー)、アルトサックス(ポール・カーマン)、テナーサックス(アルバート・ウィン)、バリトンサックス(カート・マガトリック)という贅沢なブラス/ホーンセクションを伴い、84年ツアーから引き続きのメンバー(アイク・ウィリス、チャド・ワッカーマン、ボビー・マーティン、スコット・テュヌス+84年ツアーには未参加だったエド・マン)に新人ギタリスト(マイク・ケネリー)を引き連れた、グランドワズー期以来の大編成も魅力ですが、何より100曲を超える膨大なレパートリーを入念なリハーサルで仕込み、新曲+カバー曲+旧曲の新アレンジ織り交ぜながらのツアーは、コンサートごとにセットリストが違い、新曲がメインの日、カバー曲満載の日、その日だけのレア曲が披露される日、お馴染みの曲のオンパレードな日など組み合わせも様々なので、どの日のコンサートを聴いても新鮮な驚きと楽しさにあふれています。しかも、リハーサルはコンサート中も続き、コンサートごとにアレンジが変えられたり、新たにレパートリーが増やされでもいたようで、リハーサルのみで本番では披露されなかった曲だけでかなりの数に上ります。さらに、このツアーでは「シークレットワード」と呼ばれる、その日のコンサートを通して盛り込まれるキーワードが設定される日があり、その日は歌詞のあちこちにキーワードが盛り込まれ、アドリブによる遊び要素が増えて、更に楽しさが倍増しています。
1988年のツアー・バンドは、アメリカ南部、中西部、そして西部の聴衆にその演奏をご披露する前に、自然消滅してしまった。しかし、アメリカ東部とヨーロッパでは、その短い存命期間内(1987年から88年にかけてリハーサルが4ヵ月、それに続くツアーが88年2月から6月)に演奏を聴いてもらえたし、高い評価をいただいた。(「The Best Band You Never Heard In Your Life」ライナーノーツより)
ツアーは3月までアメリカ国内を回り、4月よりヨーロッパに移ります。アメリカでは、観客に選挙人登録を行わせるために途中休憩を挟み、コンサート本編は2部制となっていましたが、ヨーロッパは大統領選も選挙人登録も無関係なため、主にアンコールまで休憩無しで演奏されるようになりました。
セットリストの中に頻出するいくつかの決まった組み合わせ
まずは、1988年ツアーにおける、コンサートごとの違いを見分けるために、その中で使われている法則について整理しておきます。コンサートごとにセットリストは変わりますが、全曲がランダムにシャッフルされるわけではなく、ある程度曲順の決まった組み合わせや、オープニングやアンコールでしか演奏されない楽曲など、ある程度グループ分けされたものを組み合わせて、自由な中にも統一感や流れの良さを保持しています。それでは、この後の説明の簡単のために、その定型フォーマットについて列記して行きます。
【新曲グループ】
“Dickie’s Such An Asshole”
“When The Lie’s So Big”
“Planet Of The Baritone Women”
“Any Kind Of Pain”
“Jesus Thinks You’re A Jerk”
1曲目は厳密には新曲ではありません(”Any Kind Of Pain”も1976年に短いインストとして演奏されています)が、他の4曲がこの組み合わせで演奏されるケースでは主にこの曲からの流れになっているので、新曲グループとしてまとめておきます。5月4日のオランダ公演までこの組み合わせは使われることになります。”Dickie’s〜”以外の曲は、公演ごとに削ったり分断したり”Any Kind Of Pain”のみ加えられたりしていますが、4曲続けて演奏される時はこの曲順になります。このツアーでは他にも”Promiscuous”、”Rhymin’ Man”、”Elvis Has Just Left The Building”などの新曲もありましたが、レギュラー的に頻繁に取り上げられたのは上記4曲でした。
【One Size Fits Allセット】
“Florentine Pogen”
“Andy”
“Inca Roads”
“Sofa”
特に”Sofa”を除く3曲は、”Florentine〜”がプレイされる限りは必ずこの流れで演奏されます。”Sofa”は使い勝手が良いため、セットリストのあらゆるところに単体で登場しますが、同アルバム収録曲なのでまとめておきました。
【アンコールグループ】
“Whipping Post”
“I Am The Walrus”
“Illinois Enema Bandit”
“I Am The Walrus”は本編中にも何度か登場していますが、”Whipping Post”、”Illinois Enema Bandit”は必ずアンコールで演奏され、この3曲はメドレー的につなげて披露される場合が多いです。
【OCLTメドレー】
“Let’s Make The Water Turn Black”
“Harry, You’re A Beast”
“The Orange County Lumber Truck”
“Oh No”
“Theme From Lumpy Gravy”
「Make A Jazz Noise Here」でお馴染みのこのメドレーは、ツアー中でも頻繁に披露されており、毎回コンサートのハイライトと言えるほどの盛り上がりを見せています。
【Tortureグループ】
“The Torture Never Stops”
“Bonanza Theme”
“Lonesome Cowboy Burt”
“The Torture Never Stops”
「The Best Band〜」でお馴染み、”The Torture〜”で”Lonesome Cowboy Burt”を挟み込み、ボナンザのテーマも混ぜ込むパターンで、本編後半に登場することが多い流れです。
【Packardセット】
“Packard Goose”
“Royal March From L’Histoire Du Soldat”
“Theme From Bartok’s Third Piano Concerto”
“Packard Goose”
「Make A Jazz Noise Here」に登場するクラシックのメドレーは”Packard Goose”にインサートされる形で披露されています。
【Beatlesメドレー】
“Norwegian Wood”
“Lucy In The Sky With Diamonds”
“Strawberry Fields Forever”
Beatlesのカバーですが、2月27日公演で”Norwegian Wood”、”Lucy In The Sky With Diamonds”の2曲をオリジナル歌詞で披露した翌日以降、”Strawberry Fields Forever”を加えた3曲をメドレー形式にした上で、歌詞をジミー・スワッガードを揶揄したものに書き換えました。このメドレーは、1曲目で”Norwegian Wood”の部分を”Texas Motel”と歌っていることから、”Texas Medley”、”Texas Motel Medley”とも呼ばれています。もう1曲、”I Am The Walrus”もカバーしていますが、こちらはこの3曲とは別扱いで、単独でセットリストの様々な場所に登場しています。
【Doo-Wapメドレー】
“The Closer You Are”
“Johnny Darling”
“No No Cherry”
“The Man From Utopia/Mary Lou”
「You Can’t Do That On Stage Anymore Vol.4」に84年の演奏が収録されていますが、88年も全く同じ曲順で披露されています。
【Stick Togetherメドレー】
“Stick Together”
“My Guitar Wants To Kill Your Mama”
“Willie The Pimp”
“Montana”
こちらも「You Can’t Do That On Stage Anymore Vol.4」でお馴染みのメドレー形式です。
【City〜Poundコンビ】
“City Of Tiny Lites”
“Pound For A Brown”
この組み合わせは絶対ではないですが、頻発しています。
【Trouble〜Penguin〜Hot Plateメドレー】
“Trouble Every Day”
“Penguin In Bondage”
“Hot Plate Heaven”
ツアー3日目から披露されているこの3曲も、例外もありますが、主にこの組み合わせで演奏されています。
【Disco〜Teenage〜Truckメドレー】
“Disco Boy”
“Teenage Wind”
“Truck Driver Divorce”
3曲目が”Bamboozled By Love”に変わることもありますが、主にこの3曲でツアー2日目から演奏されています。
【I Ain’t〜Love Ofコンビ】
“I Ain’t Got No Heart”
“Love Of My Life”
ツアー4日目から披露されているこの組み合わせも、例外もありますが、少なくとも”Love Of My Life”は”I Ain’t Got No Heart”の後以外では演奏されていません。
【Joe’s〜Why Doesコンビ】
“Joe’s Garage”
“Why Does It Hurt When I Pee”
このツアーで”Joe’s Garage”がプレイされる場合、次の曲は必ず”Why Does It Hurt When I Pee”です。
【Peaches〜Stairwayコンビ】
“Peaches En Regalia”
“Stairway To Heaven”
どちらも単独で登場することも多い、このツアーでも目玉の曲ですが、この組み合わせでの演奏頻度も非常に多いです。
【We’re 〜Alienコンビ】
“We’re Turning Again”
“Alien Orifice”
「You Can’t Do That On Stage Anymore Vol.6」でもお馴染みのペアですが、本ツアーでも何度もこの流れで演奏されています。”Alien Orifice”は”Packard Goose”に続いて演奏されるケースも多いです。
【オープニングパターン】
“Black Page #2”
“Stinkfoot”
“Heavy Duty Judy”
コンサートの1曲目は、上記3曲のいずれかになります。2月10日ワシントン公演のみ、ジャーナリストのダニエル・ショールを迎えて”It Ain’t Necessarily So”を歌わせたり”Danny Boy”、”Summertime”を引用したりと、完全にイレギュラーなスタートになっています。
【エンディングの常連】
“Strictly Genteel”
“Watermelon In Easter Hay”
“Illinois Enema Bandit”
基本的に締めくくりの曲は決まりがなく、様々な曲が最後に置かれていますが、上記3曲は特にコンサートの最後にマッチする曲として重宝していたようです。USツアー後半では”America The Beautiful”を演奏されることもあり、この辺りはザッパの愛国心とも皮肉とも取れる感じがしますね。
USツアーの流れ
ツアーは1988年2月2日にニューヨークの州都・オールバニからスタートします。この日の公演は初日ということもあり、このツアーでの半レギュラーとなる【新曲グループ】を披露しています。この初日のセットリストがツアーの基本形態となりそうなところですが、ところが初日に披露された”Dancin’ Fool”は全81公演中たった6回しか演奏されず、未だ公式では未発表です。
そして2日目には【Disco〜Teenage〜Truckメドレー】とこれまた新たな(そして2021年7月現在公式では未発表の)ナンバーがドカンと投入されます。
3日目に至っては、本ツアーのオープニングの常連”Black Page #2″から、前半は全て初出し(”Chawna In The Bushwop”、”Lucille Has Messed My Mind Up”、【OCLTメドレー】、【Trouble〜Penguin〜Hot Plateメドレー】、”Montana”、【City〜Poundコンビ】)、後半も【新曲グループ】で本編を締めると、アンコールは”Catholic Girls”、”Crew Slut”、”Andy”、”Inca Roads”、”Illinois Enema Bandit”と全て初出し。
4日目、”Stinkfoot”、【I Ain’t〜Love Ofコンビ】、”Bamboozed By Love”、”Peaches En Regalia”、”Heavy Duty Judy”、【Doo-Wapメドレー】、”Watermelon In Easter Hay”が追加。この時点でレパートリーは既に50曲近くに及んでいます。
5日目にニューヨークからワシントンへ移り、”Cosmik Debris”が追加。6日目に”Florentine Pogen”、”Black Napkins”が追加され、7日目には”Sinister Footwear II”、”Bacon Fat”、”Stolen Moments”の3曲が加わり、ペンシルヴァニア州フィラデルフィアへ移ります。
ペンシルヴァニア州フィラデルフィアでは、初日に”Uncle Remus”、” Bobby Brown”、翌日に”Alien Orifice”、”Zomby Woof”、”Eric Dolphy Memorial Barbecue”、”Big Swifty”、”Advance Romance”の5曲が加わり、3日目に”Zoot Allures”が追加。
コネチカット州ハートフォードでは初日に”Cruising For Burgers”、翌日に【Joe’s〜Why Doesコンビ】、”Eat That Question”。
13日目のマサチューセッツ州ボストンでようやく新曲登場がストップしますが、翌日には”Find Her Finer”、”Outside Now”、”Yo Cats”の追加……と、ほぼ2日と空けずにセットリスト候補はどんどん増え続けていきます。また、ツアー中一度しか演奏されなかった曲は、カバー(”Purple Haze”、”Murder By Numbers”など)や即興演奏の延長のようなもの(や”Take Me Out To The Ball Game”のようなノベルティー的なもの)を除くと、”Jezebel Boy”、”Stevie’s Spanking”、”Honey Don’t You Want A Man Like Me”、”The Dangerous Kitchen”しかありません。他は全て、2回以上演奏されているのです。
これらを公演日ごとに自在に組み替えながらツアーは猛烈なテンションを保ったまま突き進みます。もちろん、ただでさえ複雑で難解な楽曲ばかりな上に、曲間のつなぎはカウント無しでBPMも全然違う、というハードさで、加えてツアー中にアレンジの変更まで起こるのですから、至るところでミスタッチ、躓き、先走り、数え間違い、やり直しが起こります。しかしそれも含めて公演ごとの違いや変化として楽しめるので、何度聴いても発見があり、聴き飽きるという事がありません。
2ヶ月間のヨーロッパツアー
東海岸からデトロイト、シカゴを回って再び東海岸を行脚した37公演の後、ヨーロッパへ飛び、フランス、ベルギー、ドイツ、イギリス、ドイツ、デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、オランダ、ドイツ、オーストリア、ドイツ、スイス、スペイン、フランス、ドイツ、オーストリア、イタリアと、2ヶ月間44公演を行います。この後、ツアーが続けられれば日本にも来たという希望的観測もありますが、事実としてはアメリカ東部と西ヨーロッパの主要国を回ったのが1988年ツアーということになります。
USツアーで候補曲がほぼ出揃ったザッパバンドは、選挙人登録を行わない分、途中休憩を挟まないセットが増え、より縦横無尽にセットリストをミックスし続けていきます。シークレットワードも荒唐無稽なものが頻発し、ザッパの遊び心が暴走しがちなところも聴きどころ。「Sausage」(4/27 ノルウェー)では、「そせっじ」とヘンテコな発音で自分たちで勝手にツボに入ってるし、「Dragonmaster」(スウェーデン 5/1)では”Any Kind of Pain”の”Whe she’s in a bold mood”の後に間を空けて客に”Dragonmaster”と言わせようとするものの反応がなかったので一旦曲を止めて改めて言わせるという展開があるし、「Haenna Hoona Haenna Hoona」(スウェーデン 4/26)なんてもう……。
フィンランドのヘルシンキでは”Whipping Post”を演奏し、1974年の伏線回収をしつつ、”Rhymin’ Man”、”Elvis Has Just Left The Building”というUS未披露の新曲も登場し、さらに”Easy Meat”、”T’Mershi Duween”、”You Are What You Is”、”Pick Me I’m Clean”とセットリストもじわじわ増やしてゆき、表面上は楽しい楽しいヨーロッパツアーが順調に進んでいるようにしか思えませんが、裏ではバンド内での衝突が起こっており、やがてイタリアで臨界点を超え、ザッパ最後のバンドは活動終了を余儀なくされました。イタリアでの8公演ではついに新曲が一曲も演奏されなかったため、バンドメンバーとしてもほぼやるべきことはやり尽くしたという気持ちや、その上で100曲以上のレパートリーを抱えたまま毎日コンディションを維持していくことにも疲弊していたのではないでしょうか。結果としては、誰が原因だとかクーデターを率先したのは誰だとか言われることになりましたが、早晩こうなって然るべき状況だったのかもしれません。それだけ、88年のザッパバンドは、世界中を探しても比肩する存在がないような、それこそトッド・ラングレンが羨ましがったとも言われる、正に”The Best Band You Never Heard In Your Life”だったということです。このタイトルに、偽りなし。
USラストコンサート
USラストコンサートが、2021年6月に、119番目のオフィシャル作品としてリリースされました。ブラックヴァイナル(カラーヴァイナルは過去に音質が悪かったことが多いので基本的には手を出しません)で購入しましたが、4枚のレコードをしっかり保護するマット仕上げのハードケースに収まり、レコードを取り出しやすくするためのリボンも仕込まれていて、非常に満足感を味わえる存在感があります。「Joe’s Garage」や「LÄTHER」とは違います。レコード8面を切り替えながら一夜の演奏を聴き続けるのは正直面倒ですが、それでもこのアナログボックスは、ザッパファンなら一家に一箱、と言いたくなるクオリティだと思います。
さて、その内容ですが、ツアー全体の出来栄えからすると、わりと平均的なレベルの公演と言えるでしょう。シークレットワードでの悪ふざけが過ぎるコンサート、イレギュラーなセットリストで度肝を抜かれるコンサートなどなど、聴きどころ・面白どころの多いツアーの中で、節目として打ち出しやすく、演奏も全体的に安定している日ということで選んだのだと思いますが、こうやって一つのコンサートとしてまとめられると、なぜザッパが複数タイトルでリリースしたのか、改めて痛感させられます。この88年ツアーの大宇宙を、一夜のパフォーマンスから把握することなど、不可能なのです。
とは言え、こうやって88年のコンサートが(一部別の日のテイクが使われてはいますが)一夜を通して追体験できるソフトが公式にリリースされたことは大変喜ばしいことです。今回は、公式初公開のビートルズカバーのお披露目という意味合いとして捉え、いずれ時がくれば、”Keep It Greasy”や”Uncle Remus”の88年バージョンも何らかの形でリリースされることを期待しつつ……。
※本記事は、The Frank Zappa 1988 Tour Projectの情報を元に作成しました。1988年ツアーに関するあらゆる情報が網羅されていますので、より詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。