この日はMusic Club JANUSにパスカルズを観に行きました。

JANUSに来たのはMM&Wを観に来て以来なので4年ぶり。当時はビルのテナントはJANUS以外ほぼ何処も入っておらず閑散としていましたが、今はどの階も飲食店が入居していますね。
パスカルズは試聴会で聴いて感動して以来、いつか観に行こうと思っていたんですが、磔磔での公演はいつもすぐにチケットが完売するので行きそびれており、この日ようやく観ることができました。
フロアには椅子が並べられており、開演20分ほど前に着くと、8割ほど埋まっている状況でした。適当に左右センター辺りの席に座り、開演時間が迫る頃には、椅子席の周囲には立ち見のお客さんがいっぱい。
ステージ上に14名のメンバーがずらりと並ぶ姿はなかなか圧巻でしたが、ほとんど生楽器で大きな音が出る管楽器はひとりだけということもあってか、音の壁が押し寄せるような感じではありませんでした。フロアも無駄な残響音が無く、聴き取りやすくうるさすぎない、耳に心地良いバランスでした。
バイオリンにバンジョーにウクレレ、口琴や茶瓶で作ったパーカッション……とジャンル特定不可能なごちゃ混ぜ編成で、それぞれが見事に調和している、という感じも無く、ところどころデコボコしていて歪な響きを持ったアンサンブルなんですが、何故かそれが実に心地良く、全体として調和しているようにさえ感じてしまう不思議。
奏者は、リーダーのロケット・マツはじめ、長いキャリアを誇るベテランから本業を別に持つメンバーまで様々なので、それがデコボコ感を生み出している理由かも知れません。しかし演奏自体がユルいとか破天荒だとか言うわけではなく、きっちりと決められた演奏を全員で忠実にこなしているという感じ。但し、石川浩司と坂本弘道以外は。
前列上手で、お馴染みのランニング姿で簡素なパーカッションとおもちゃ楽器を駆使する石川浩司は、時折曲に合わせて芝居がかった動きをしてみせたり、釣り竿に鈴を付けて客席に振ってみたりと、バンドのムードメーカーとして終始動き回り、時折グッと来るような歌声や器楽音を聴かせながらも、何度も聴衆からの笑いを誘います。
休憩明けの後半、ステージに上がってきた時にはひとりアイスキャンデーを食べており、マツ氏に「食べ終わらないうちに演奏始まったらどうすんの」と訊かれても「食を優先します」と全く動じず、黙々と食べ続けていました。
坂本弘道を生で観たのは、おそらくフジロックにシカラムータと渋さ知らズで出た2003年以来。当日は確か渋さがオレンジコートをキュレーションしていて、RuinsやSun Ra Arkestraに挟まれてシカラムータも出ており、不破大輔が「坂本弘道の火花を渋さでやって欲しいから呼んだ」というようなことを言っていたと思うんですが、パスカルズでも健在なうえ、チェロを肩から下げてギターのようにかき鳴らしたり電気ドリルを擦り付けたりカオシレーター擦りまくったりと、眉ひとつ動かさず痛快なパフォーマンスを炸裂させていました。
曲の途中で坂本氏がステージを去る場面があり、どうしたのかと思えばフロアに現れ、立ち見のお客さんに混じってステージを観ていました。相変わらずのポーカーフェイスで何を考えているんだろう……と思っていたら、いきなりその場でカオシレーターを演奏し始め、気付いたお客さんはびっくり。そのままお客さんの間を練り歩きながら演奏していると、石川氏も参戦。二人揃って大いに盛り上げてステージへと戻って行きました。
パスカルズの曲は2拍子のタテノリな曲や、陽気な曲も多いですが、印象的なのは3拍子の物悲しい曲や異国から引いてきたようなビートやスケールのペーソスのにじみ出た曲で、それらが入り交じった結果、多幸感が溢れながら、死の世界を思い浮かべてしまったり、歌詞も何も無いのに人生のこれまでとこれからについて想いを馳せてしまったり、何故か心細く、寂しくなるようなイメージが頭の中で広がっていきました。
まるで、生と死の狭間にパスカルズという音が滞留しているかのような、人の命の強さと儚さを歌っているかのような……。
心の中のデリケートなところに触れられている感覚に襲われながら、この世ではない所から鳴らされているような音楽に浸り切った約2時間半。帰路、夢のような歌の世界から浮き世に徐々に戻りながら、少しほっとしたような気分にすらなりました。それでも後味として残るこの寂しさと切なさは、一体何なんだろう。
| 17才 | |
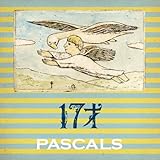 |
Pascals
オフィス・ロケッタ 2012-09-01 |