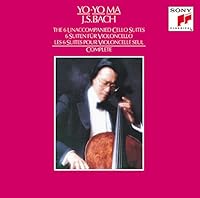この日はヒビキミュージックサロン リーヴズに、細谷公三香無伴奏チェロリサイタルを観に行きました。

会場は、西天満にあるビルの一室。ステージは無く、以前は何の店だったのか、壁に装飾や手書き文字など、若干の名残のあるフラットな部屋で、椅子を並べて100人弱という広さでした。
プログラムは以下。
無伴奏チェロ組曲より 第1番 ト長調(バッハ)
無伴奏組曲(カサド)
〜休憩〜
シャコンヌ形式のカプリス(クレンゲル)
無伴奏チェロソナタ(ヒンデミット)
アローン(ソッリマ)
1曲目はバッハ無伴奏チェロの第1番。冒頭からミスがあったり弓が悲鳴を上げたりする瞬間があったりはしましたが、ポリフォニーの重なりが浮かび上がるような立体感は、生の無伴奏を聴くとよりリアルに伝わってきました。
演奏が固く感じたのは初めの曲だったからなのか、バッハの曲だったからなのかは分かりませんが、続くカサドの無伴奏組曲では、チェロの音量も増し、熱く激しく疾走する演奏が聴けました。フラメンコを彷彿とさせる和音やピチカートが随所に現れ、たった4弦の低音楽器一台で演奏しているとは思えないような、複数人によるアンサンブルを聴いているようなダイナミックな迫力に溢れていました。バッハよりも、こういう演奏の方が得意なのかな、と思ったり、厳格なバッハの曲では粗が目立ちやす過ぎるのかな、と思ったり。
そして、演奏以上に目を引いたのが演奏していたチェロ。開演前にかけて置かれていた時から、その年季の入った風貌に見とれていましたが、1700年代のものだそうで、背中に穴があり、肩からかけるためのストラップを通すためのものなのだそうです。ピンも付いていましたが、きっと後付けなのでしょう。
休憩を挟んで、クレンゲル、ヒンデミットと、カサドに続いて聴き慣れない無伴奏チェロ曲が続きますが、息切れしそうなクレンゲルも前衛的な表現を活写するヒンデミットもそれぞれ聴き応えがあり、心地良い緊張感を保ったまま(息抜きに曲の初めに簡単な楽曲解説があったのも良かったです)、最後のソッリマへ辿り着きました。
この日の目当ては、バッハとこのソッリマの演奏でしたが、ゆっくりと弓弾きしながら左手でピチカートする静かなパートから一転、弓と右手が激しく動き回るコントラストと息を飲む疾走感はなかなかの迫力でした。男性が弾くソッリマよりも繊細でスマートに聴こえたのは、女性が弾いていることへの思い込みによるものでしょうか。
休憩を挟んで1時間半ほどの短い演奏会でしたが、バリエーション豊かなプログラムで飽きさせず、密度の濃い演奏で物足りなさも無く、チェロ独奏を気軽に楽しめるような良質なイベントでした。会場の音響も、ハコの存在を忘れさせる自然な響きで好感が持てました。